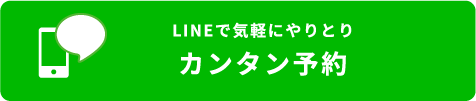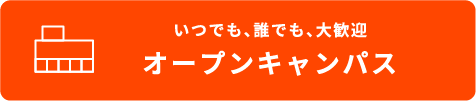普通貨物自動車ってどんな車?商用車との違いと分類ポイントを解説

「4ナンバーと1ナンバーって何が違うの?」
「トラックを買いたいけど、どんな免許が必要なんだろう?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
荷物の運搬に便利な「普通貨物自動車」ですが、最大積載量や車両総重量によって分類が細かく分かれており、ナンバー区分や免許、維持費、活用シーンなど、選ぶ際に知っておきたい情報がたくさんあります。
本記事では、
- 道路運送車両法に基づく「普通貨物自動車」の定義
- 4ナンバー/1ナンバーの違いと分類基準
- 登録・運転免許・車検などの手続き
- トヨタ・日産・三菱ふそう・いすゞなど代表車種の特徴
- 維持費・保険料・リース/レンタル活用の注意点
といった【選び方・使い方・注意点】をわかりやすく解説します。
これから導入を考えている事業者・個人事業主の方にもおすすめの内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
普通貨物自動車の定義と法的根拠

道路運送車両法における車両区分
普通貨物自動車は、道路運送車両法第2条で定められる貨物自動車の区分のひとつです。この法律では、自動車を「普通」「中型」「大型」の三つに分け、そのうち「普通」の枠組みに該当する貨物用途の車両を普通貨物自動車と呼んでいます。
具体的な区分基準は以下のとおりです。
- 車両総重量:3.5トン以下
- 最大積載量:2.0トン以下
- 乗車定員:10人以下(貨物車は通常0~2名)
上記のいずれかの基準を超えると「中型貨物自動車」(車両総重量3.5トン超~7.5トン以下、最大積載量2.0トン超~4.5トン以下)や「大型貨物自動車」(車両総重量7.5トン超または最大積載量4.5トン超)に分類されます。
普通貨物自動車と商用車の違い
「普通貨物自動車」はあくまで法律上の車両区分ですが、「商用車」という呼び方はメーカーや販売店、ユーザーの間で使われる用途・仕様を表す俗称です。
主な違いは次のとおりです。
- 法的区分 vs. 用途名称
普通貨物自動車は道路運送車両法で定義されるカテゴリー、商用車は「荷室を広く取ったバン」「貨物運搬を想定した装備」の総称です。 - ナンバープレートの区分
普通貨物自動車は4ナンバー(事業用)または1ナンバー(特殊用途)の区分ですが、商用車として売られるモデルは5ナンバー登録の乗用貨物兼用仕様になる場合もあります。 - 税金・保険の取り扱い
普通貨物自動車は貨物用途に特化した登録で自動車税や自賠責保険料が貨物車基準になる一方、商用車扱いで乗用車登録すると税制や保険料率も乗用車扱いとなります。
普通貨物自動車の分類ポイント

普通貨物自動車を正しく区分・選択するには、最大積載量や車両総重量の数値基準と、ナンバープレートの区分ルールを押さえることが不可欠です。本章では、それぞれのポイントを詳しく解説します。
最大積載量と車両総重量
最大積載量の基準
最大積載量とは、車両が積載できる貨物の重量上限を示す数値です。道路運送車両法では、車両の寸法や用途に応じて分類が定められており、普通貨物自動車では最大積載量が2トン以下であれば小型貨物自動車(4ナンバー)に該当します。なお、商用トラックとしての利用を考える際には、自動車税の税率区分や保険料率もこの数値をもとに決まるため、経済的負担にも直結します。
車両総重量の計算方法
車両総重量は「車両重量(車両自重+乗員・燃料などの付加重量)+最大積載量」で算出します。たとえば、車両重量が2.5トン、最大積載量が1.5トンの車両であれば、車両総重量は4.0トンとなります。車両総重量が5トン以下であれば4ナンバー、5トンを超えると1ナンバーの判定基準にも関わるため、登録時の車検証記載事項や継続検査にも影響を与えます。
ナンバープレート区分 4ナンバーと1ナンバー
4ナンバー貨物の特徴
4ナンバーは「小型貨物自動車」として登録される区分で、以下の条件を満たします。
・最大積載量が2トン以下
・車両総重量が5トン以下
・全長5m以下、全幅2m以下、全高3m以下
4ナンバー車は自動車税や自賠責保険料が1ナンバーに比べて安価で、法人や個人事業主の日常的な配送業務や宅配便、小売店の納品など、多くの物流シーンで利用されています。
1ナンバー貨物との比較
1ナンバーは「大型貨物自動車」の区分で、4ナンバーの上限を超える貨物車両に適用されます。最大積載量や車両総重量が4ナンバー基準を超えるため、自動車税や重量税、自賠責保険料の負担が増加。また、車検周期や点検項目も厳格化されるため、維持費・メンテナンスコストも高くなる点に注意が必要です。一方で、大量輸送や大型機材の運搬など、4ナンバー車では対応できない業務に適しています。
普通貨物自動車を運転するための免許と登録手続き

必要な運転免許の種類と条件
普通貨物自動車(最大積載量2トン以下、車両総重量5トン以下)を運転するには、車両の総重量や取得時期に応じた免許が必要です。以下の条件を満たしているか確認しましょう。
普通自動車免許は、2007年(平成19年)6月1日以前に取得した場合、車両総重量5トン以下かつ最大積載量3トン以下の貨物自動車を運転できます。しかし、それ以降に取得した場合は車両総重量3.5トン以下、最大積載量2トン以下に限定されます。
準中型自動車免許を取得すると、車両総重量7.5トン以下かつ最大積載量4.5トン以下の普通貨物自動車まで運転可能です。普通免許の制限を超える場合や、後からより大きな車両を運転したい場合はこちらが必要です。
中型自動車免許は車両総重量11トン以下、最大積載量6.5トン以下の車両を運転できますが、普通貨物自動車の範囲を超えているケースが多いため、主に中型トラックを想定する際に取得します。
上記免許を取得する際には、年齢要件(18歳以上)や適性検査、学科および技能試験が課せられます。教習所を利用する場合は所定の教習時間を修了し、仮免許取得後の路上教習も含めたカリキュラムに従ってください。
車検と継続検査のポイント
普通貨物自動車は、自家用乗用車よりも頻繁かつ厳格な車検・継続検査が必要です。以下のポイントを押さえて、適切に手続きを進めましょう。
初回車検の期限は、新車登録から3年後です。その後は2年ごとの継続検査(車検)を受ける必要があります。事前に日程を調整し、必要書類や費用を準備しましょう。
必要書類は以下のとおりです。
- 車検証
- 自賠責保険証明書
- 自動車税納税証明書
- 点検整備記録簿(24か月点検の記録)
整備・点検は、法定24か月点検に基づく内容をディーラーや指定工場で実施します。ブレーキや灯火類、排出ガス、足回りのチェックを確実に行い、整備不良による再検査を防ぎましょう。
予約と費用は、陸運局や認証工場で行います。車検基本料金のほか、自賠責保険料、重量税、印紙代が必要です。事前に見積もりを取り、業者ごとの費用差を比較するとコスト管理が容易になります。
普通貨物自動車の活用シーンと代表的な車種

普通貨物自動車は、その積載容量とサイズバリエーションを活かし、都市部の配送から建築資材の運搬、引越しまで幅広いシーンで活躍します。特に小型から中型トラックは機動性と積載力のバランスに優れ、多彩な業務用途に対応可能です。
小型から中型トラックの使用例
例えば、ネット通販の急増に伴い都市部のラストワンマイル配送では小回りの利く小型トラックが重宝されます。また、建築現場への資材運搬では荷台高が抑えられた低床仕様が現場での積み下ろし作業を効率化。さらに、家具や家電の運送・引越し用途では中型サイズのロングボディ仕様が大物の積載に対応し、安定した燃費性能と耐久性で業務を支えます。
国内で流通している代表車種
トヨタ ハイエース バン
小型商用バンの定番であるハイエースは、荷室空間の広さと多彩なオプションが魅力。標準・ワイド・ロングの3タイプをラインナップし、荷物の形状や量に合わせた選択が可能です。ディーゼルエンジン搭載モデルは優れた燃費性能と高トルクを両立し、コスト重視の配送業務に適しています。
日産 キャラバン バン
キャラバンはシンプルで堅牢なボディ設計が特長。標準・ロングボディに加え、ハイルーフモデルを展開し、立体ラックなどの積載物にも対応。メンテナンス性に優れ、リセールバリューも高いため、長期的な運用コストを抑えたい事業者に人気です。
三菱ふそう キャンター
中型トラックの代表格であるキャンターはキャブオーバー形状により、最小回転半径の小ささを実現。高出力ディーゼルエンジンと堅牢なシャシーにより、建設現場や物流センター間の長距離輸送にも対応します。最新モデルではADAS(先進運転支援システム)を標準装備し、安全性も強化されています。
いすゞ エルフ
エルフは豊富な車型バリエーションが魅力で、平ボディ・ウイング・冷凍冷蔵仕様など多様な荷台を用意。高い燃費性能と低床プラットフォームにより、停車と積卸しを繰り返す配送業務に最適です。いすゞ独自のアフターサービス体制も手厚く、稼働率を維持しやすいのが強みです。
普通貨物自動車を選ぶ際の注意点

普通貨物自動車を導入する際は、導入コストだけでなく、維持にかかる総合的なコストを事前に把握し、長期的な視点で比較検討することが重要です。
燃費と維持費の比較
燃費性能は車種やエンジン仕様、積載量によって大きく変動します。たとえば、ディーゼルエンジン搭載の小型トラックであれば、カタログ上10km/L前後の燃費を実現するモデルもありますが、実際には走行条件や荷重によって8km/L程度まで落ち込むこともあります。
また、タイヤ交換やオイル交換などの定期メンテナンス費用も車両のサイズや使用頻度に応じて高くなるため、年間の総走行距離と合わせて具体的な見積もりを取ることが必要です。
保険料と税金の違い
普通貨物自動車は、車両総重量や最大積載量に応じて自賠責保険料や重量税が変わります。たとえば、車両総重量3.5トン以下の4ナンバー貨物車では、自賠責保険が1年あたり約30,000円前後、重量税が新車登録時に20,000〜25,000円程度となることが一般的です。
さらに、任意保険料も補償範囲や運転者年齢条件によって変動するため、複数の保険プランを比較し、必要な補償を過不足なく確保することが肝要です。
レンタカーとリース利用時のポイント
購入ではなくレンタカーやリースでの利用を検討する場合、契約期間や走行距離制限、保守メンテナンスの範囲を必ず確認しましょう。短期間のスポット利用であればレンタカーが適しており、月額固定で導入負担を抑えたい場合はリース契約が有効です。
リース契約では、メンテナンスコミコミプランを選ぶと車検や定期点検、オイル交換などが一括で管理でき、突発的な出費リスクを軽減できます。ただし、契約終了時の返却状態に応じた費用負担条件を事前にしっかり確認しておきましょう。
まとめ

普通貨物自動車は、最大積載量2トン以下かつ車両総重量5トン以下の貨物車を指し、道路運送車両法に基づいて4ナンバーや1ナンバーで区分されます。商用車との違いは積載量基準や車検頻度、税制面の取り扱いにあります。
運転には普通免許で対応可能ですが、車検や継続検査のスケジュール遵守が必要です。代表的な車種としてはトヨタ ハイエースバン、日産 キャラバンバン、三菱ふそう キャンター、いすゞ エルフが挙げられます。
選ぶ際は燃費や維持費、保険料、税金を総合的に比較し、レンタカーやリース利用も検討しましょう。用途に合った車種選定と適切な管理で、コスト削減と安全運行を両立できます。